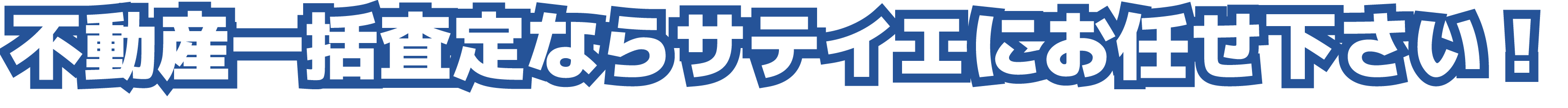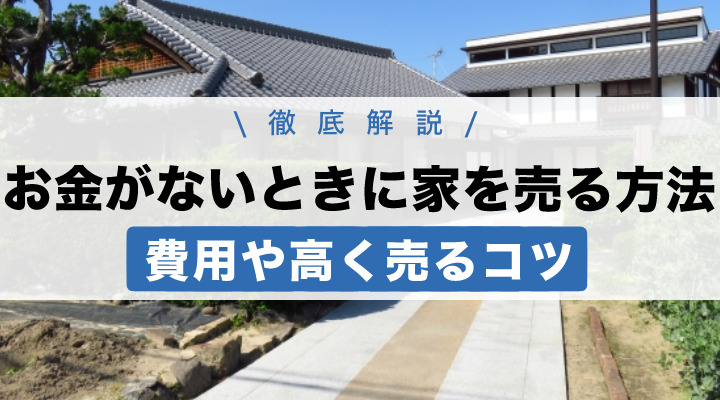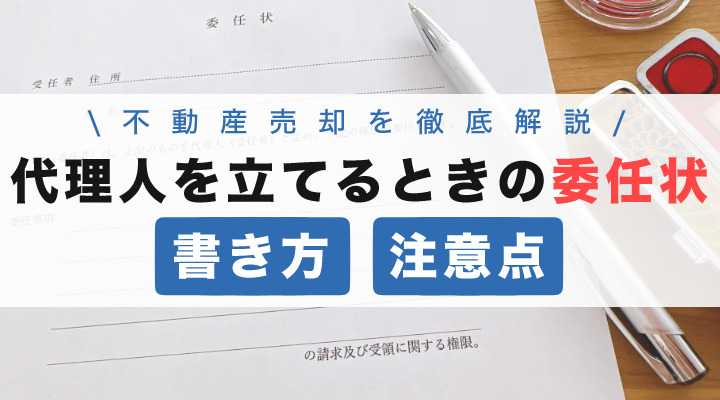2023.07.26
住み替えの税金を総まとめ|節税方法や税金控除の特例も紹介

「住み替えはどれくらい税金がかかるの?」
「住み替えの節税方法や税金控除を知りたい!」
このようにお悩みではありませんか?
住み替えに限らず不動産の売却や購入を行うと、取引した金額や利益額に応じて税金が発生します。
そこで重要になるのが、節税方法や税金控除の特例です。
この記事では、住み替えで発生する税金、税金が発生した場合の節税方法や税金控除の特例などを紹介します。
これから住み替えをしようと考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
住み替えの税金総まとめ|どんな税金が発生する?
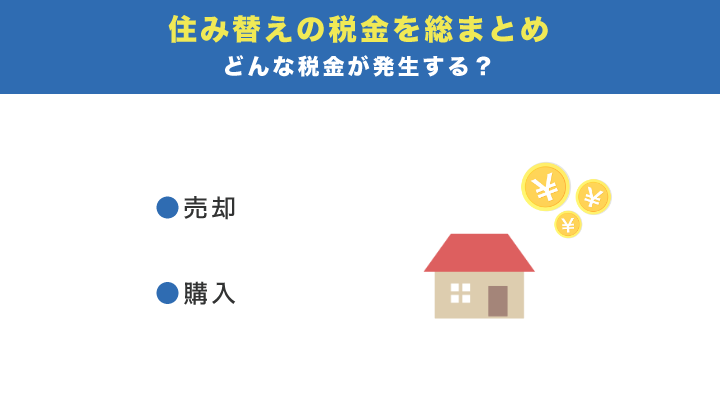
住み替えを行うと、不動産の売却と購入それぞれで税金が発生します。
まずは購入・売却でかかる税金について簡単に確認しましょう。
売却でかかる税金
売却でかかる税金は主に以下の3種類です。
| 税金 | 金額の詳細 |
|---|---|
| 印紙税 | 高額取引の契約書にかかる税金。 不動産売却では10,000円~200,000円 |
| 登録免許税 | 不動産の抵当権を抹消するために必要な税金。 1,000円/件(土地と物件に必要) |
| 譲渡所得税 | 不動産売却で利益が発生した時に発生する税金。 利益額の10%~39%(所有年数などによって異なる) |
メインとなるのは、譲渡所得税です。
ただし、譲渡所得税については特例を利用することで控除することもできるため、控除条件などをしっかり確認しましょう。
購入でかかる税金
続いて、購入で掛かる税金は主に以下の4種類です。
| 税金 | 金額の詳細 |
|---|---|
| 印紙税 | 高額取引の契約書にかかる税金。 不動産売却では10,000円~200,000円 |
| 登録免許税 | 不動産登記の名義を変更するために必要な税金。 固定資産評価額×税率(物件タイプなどで異なる) |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した時に発生する税金。 固定資産評価額の4%(軽減税率などもあり) |
| 贈与税 | 住宅を貰った場合や資金援助を受けた場合に発生する税金。 (固定資産評価額 – 110万円)×税率 – 評価額による控除額 |
メインとなるのは、不動産取得税です。
贈与税については、住宅を貰った場合や資金援助を受けた場合にのみ発生するため、当てはまる方はチェックするようにしましょう。
購入・売却のより詳しい税金については、次の項目から解説します。
住み替えの売却でかかる税金
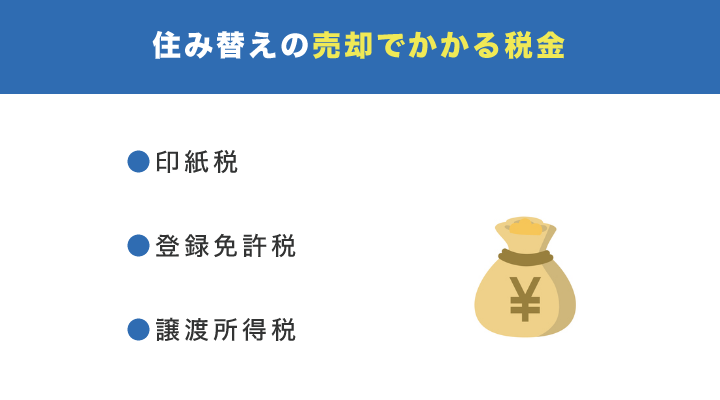
それではここからは、住み替えでかかる税金のより細かな内容についてみていきます。
まずは売却で発生する3つの税金についてみていきましょう。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
印紙税
印紙税は「日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など
に課税される税金」のことです。(国税庁:印紙税の手引より)
不動産売却においては、売却する金額に応じて印紙税が異なります。
| 売却金額 | 印紙税 | 軽減印紙税 (令和6年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
印紙税は契約する発行部数分だけ必要です。
例えば、1,500万円の契約書を2枚作る場合(自分の文と相手の保管用など)は、20,000円×2枚で合計40,000円の印紙税が発生します。
なお、契約書をコピーすることで印紙税を節約することもできますので、買主と相談して問題なければコピーで対応すると良いでしょう。
登録免許税
登録免許税は、抵当権の抹消手続きに必要な税金のこと(法務省より)です。
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は、抵当権の抹消手続きを行わなければなりません。
抵当権の抹消手続きにかかる税金は、不動産1つにつき1,000円です。
戸建てで土地と物件どちらも住宅ローンを掛けている場合は、2つ分の抵当権を抹消しなくてはならないため、2倍の2,000円かかります。
なお、不動産売却においては抵当権の抹消を司法書士に依頼することが多いです。
司法書士に依頼した場合は依頼料として20,000円~30,000円必要になりますので、その点も把握しておきましょう。
譲渡所得税
譲渡所得税は不動産売却で利益が出た時に発生する税金のことです。
不動産売却で必要な税金のうちメインになるのが、この譲渡所得税になります。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得税 =「(売却価格)-{(取得費用)+(売却費用)}」×税率
それぞれの費用についてまとめると以下の通りです。
| 名称 | 料金の詳細 |
|---|---|
| 売却価格 | 不動産の売却価格。 |
| 取得費用 | 不動産の購入価格+購入に掛かった諸費用。 リフォーム代金や契約時の仲介手数料など、諸々の費用も含まれる。 経過年数や償却率などで細かな料金を計算する。 なお、購入時の金額を証明できない場合は5%で算出。 |
| 売却費用 | 売却に掛かった諸費用。 仲介手数料やリフォーム代など、諸々の費用も含まれる。 |
| 税率 | 所有期間が5年以内:39.63% 所有期間が5年を超える:20.315% 軽減税率(10年以上):10%~ |
譲渡所得税については、さまざまな特例を適用することで大幅に控除することが可能です。
適用可能な特例については後述しますので、しっかりチェックしておきましょう。
住み替えの購入でかかる税金
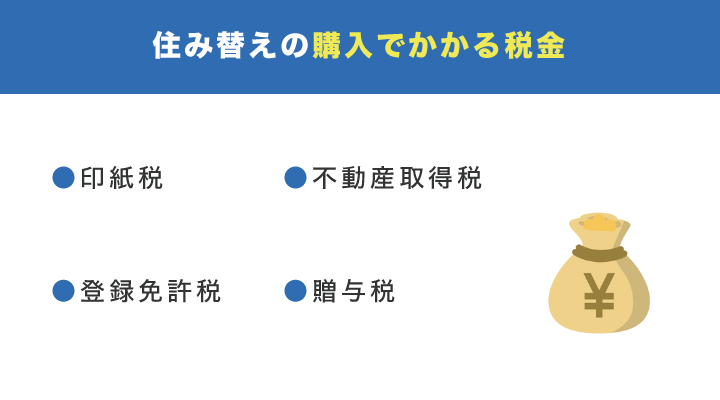
続いて購入時にかかる税金についてです。
購入時にかかる税金は贈与税も含めると、全部で4種類あります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 贈与税
それぞれの税金についてみていきましょう。
印紙税
印紙税は不動産売却時と同様の契約書に発生する税金のことです。
税金の費用についても売却時と同様で、10,000円~200,000円の税金が課税されます。
複数枚の請求書を発行する場合は、その分の費用が発生するため注意してください。
登録免許税
不動産購入時には「不動産登記の名義変更」のための税金が発生します。
税金で掛かる費用は、「固定資産税評価額×税率」です。
不動産の名義変更で発生する費用をまとめると以下の通りになります。
| 購入する不動産 | 税率 | 軽減税率 (2024年まで適用可能) |
|---|---|---|
| 土地の名義を変更する | 2.0% | 1.5% |
| 物件の名義を変更する | 2.0% | 0.3% |
| 物件に名義を登録する (新規物件購入時) | 0.4% | 0.15% |
| 住宅ローンを借りる | 0.4% | 0.1% |
購入する物件や中古かどうかなどによっても異なるため、しっかり確認しておきましょう。
なお、一般的に登記の変更などは司法書士に依頼します。
司法書士に依頼する場合は追加で50,000円~100,000円の費用が発生しますので、依頼する場合は追加の料金も把握しておきましょう。
不動産取得税
続いて3つ目が、不動産を取得した際に発生する不動産取得税です。
不動産取得税は登録免許税と同様に「固定資産税評価額×税率」で計算されます。
税率の詳細は以下の通りです。
| 購入する不動産 | 税率 | 軽減税率 (2024年まで適用可能) |
|---|---|---|
| 土地 | 4.0% | 3.0% (さらに固定資産税評価額を半額で計算する) |
| 物件 | 4.0% | 3.0% |
| 土地+物件 | 4.0% | 3.0% |
また、この軽減税率に加えて以下の条件を満たすことで軽減を受けられます。
- 居住用の不動産であること
- 延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 新耐震基準に適合していること
軽減される内容は以下の通りです。
| 購入する不動産 | 軽減内容 |
|---|---|
| 土地 | ・45,000円 ・(1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×床面積の2倍×3% ※上記いずれかの高い額を税額から控除(控除による0円になるケース有) |
| 物件 | 新築:固定資産税評価額から1,200万円を控除して計算 ※(固定資産税評価額 – 1,200万円)×3%のような形式 中古:築年数に応じて100万円~1,200万円を控除して計算 ※計算方法は新築と同様 |
かなりの税額を控除されるため、状況によっては0円になるケースもあります。
そのため、しっかり確認してから不動産取得税を支払うようにしましょう。
贈与税
贈与税は、住宅を貰った場合や購入の資金援助を受けた場合に発生する税金です。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
{固定資産税評価額(贈与額)- 110万円}×税率 – 控除額
贈与税に関しては、贈与される対象によって税率と控除額が異なります。
| 贈与額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円以上 | 55% | 400万円 |
| 贈与額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円以上 | 55% | 640万円 |
いずれも「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参照。
贈与された場合は、上記の税率を参照し計算してみてください。
住み替えで使える税金控除の特例
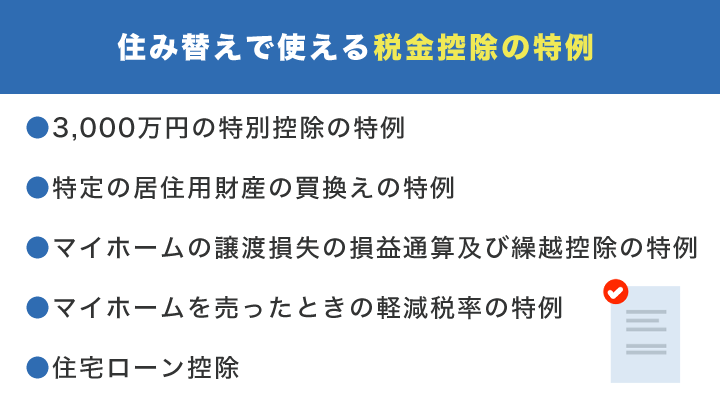
住み替えで使える税金控除の特例はさまざまありますが、基本的には以下の5つです。
- 3,000万円の特別控除の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 住宅ローン控除
それぞれの特例についてみていきましょう。
3,000万円の特別控除の特例
不動産の売却でメインに適用されるのが「3,000万円の特別控除の特例」です。
3,000万円の特別控除を利用することで、売却で発生した譲渡所得(利益分)の最大3,000万円を控除できます。
適用条件は以下の通りです。
- マイホームもしくは住まなくなってから3年以内に売却すること
- 過去2年間に同じ特例を受けていないこと
- 過去2年間にマイホーム売却による損益通算および繰越控除を受けてないこと
- 過去2年間にマイホームにまつわる特例を受けていないこと
- 売った家屋や敷地についての収用等の特別控除を受けていないこと
- 売り手と買い手が親族などの特別な関係でないこと
マイホームの売却に関しては、この特例を利用することでほぼ帳消しにできます。
ただし後述しますが、その他の特例と併用することはできませんので、しっかり自分がお得になる特例を見極めてから利用するようにしましょう。
特定の居住用財産の買換えの特例
住み替えで特にお得なのが「特定の居住用財産の買換えの特例」です。
この特例を利用することで、住み替えの売却時に発生する譲渡所得税を次のマイホーム売却時まで持ち越すことができます。
ただし、免除されるだけでなく将来に持ち越されるだけですので、その点は注意が必要です。
特定の居住用財産の買換えの特例の適用条件は以下の通りになります。
- マイホームもしくは住まなくなってから3年以内に売却すること
- 過去2年間に同じ特例を受けていないこと
- 過去2年間にマイホーム売却による損益通算および繰越控除を受けてないこと
- 売ったマイホームと購入したマイホームが日本国内にあること
- 過去2年間にマイホームにまつわる特例を受けていないこと
- 売却代金が1億円を超えていないこと
- 売った家屋や敷地についての収用等の特別控除を受けていないこと
- 売り手と買い手が親族などの特別な関係でないこと
- 売った人の居住期間と家屋自体の所有期間が10年を超えていること
- マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間でマイホームを買い替えること
- 買い替えるマイホームが25年以内に建築されていること
基本的に「購入額が売却額を上回る場合」に適用可能です。
条件が多くなっているため、しっかりと確認してから申し込むと良いでしょう。
マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住み替えの不動産売却で損失が出た場合は、「マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用できます。
この特例はマイホームの売却で出た損失額分を、その他の所得から控除できる特例になります。
適用条件は以下の通りです。
- マイホームもしくは住まなくなってから3年以内に売却すること
- 所有年数が5年を超えていて日本国内にあること
- マイホームに係る償還期間が10年以上の住宅ローンが残っていること
- (買い替え時のみ)10年以上の住宅ローンを有していること
- 売り手と買い手が親族などの特別な関係でないこと
- 過去2年間にマイホームにまつわる特例を受けていないこと
- 合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用不可能
損失額分を控除できるのは、売却から3年間のみです。
3年以降は控除できる額が残っていたとしても控除できませんので、注意してください。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
特例とは異なりますが、10年以上所有したマイホームを売却する場合は特別な軽減税率が適用されます。
適用後の税率は以下の通りです。
| 所有年数 | 税率 |
|---|---|
| 長期譲渡所得 (所有期間が5年を超える不動産) | 譲渡所得の20.315% |
| 長期譲渡所得 (所有期間が10年を超える不動産) | 6,000万円以下:譲渡所得の10% 6,000万円超え:(譲渡所得 – 6,000万円)× 15% + 600万 |
続いて適用される条件は以下の通りです。
- マイホームもしくは住まなくなってから3年以内に売却すること
- 売った年の1月1日において売った不動産の所有期間が10年を超えていること
- 過去2年間に同じ特例を受けていないこと
- 過去2年間にマイホームにまつわる特例を受けていないこと(3,000万特別控除は除く)
- 売り手と買い手が親族などの特別な関係でないこと
なお、この特例に関しては他の特例と併用可能です。
3,000万円控除や買換えの特例とも併用できますので、10年以上所有している方はしっかり条件を確認して適用しましょう。
住宅ローン控除
不動産の購入時に住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン控除が適用できます。
住宅ローン控除は、住宅を購入してから最大13年間にわたり、「年末時点での住宅ローン残高の0.7%」分を所得税や住民税から控除できる制度のことです。
住宅ローンの金額にもよりますが、最大100万円を超える控除も可能なため、適用できる方はしっかり適用しましょう。
適用条件は以下の通りです。
- 住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
- 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
- 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
ただし、売却時に使える3,000万円控除などとは併用できません。
そのため、どの特例がお得になるかをしっかり確認してから、使う特例を決めるようにしましょう。
住み替えをお得に行う節税方法
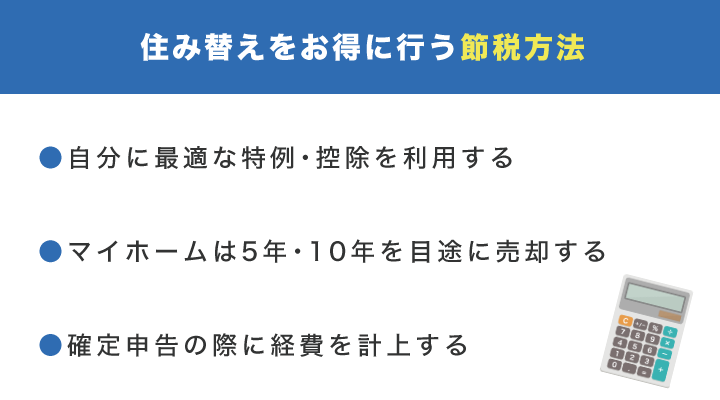
最後に住み替えをお得に進めるために節税方法を紹介します。
- 自分に最適な特例・控除を利用する
- マイホームは5年・10年を目途に売却する
- 確定申告の際に経費を計上する
それぞれの点についてみていきましょう。
自分に最適な特例・控除を利用する
不動産の特例を利用する際は、自分にあった最適な特例を利用するようにしましょう。
すでに紹介してきた通り、不動産に関する特例は併用できないものがほとんどです。
そのため、それぞれの特例を比較した上でどれがお得になるかを計算する必要があります。
「どれがお得になるか分からない…。」という場合は、税理士に相談するのも一つの手です。
ただし、依頼する費用がかかってしまうため、その点は注意してください。
マイホームは5年・10年を目途に売却する
マイホームは譲渡所得税の税率が変わる5年・10年を目途に売却するようにしましょう。
5年・10年を目途に以下のように税率が変動します。
- 5年以下:税率39.625%
- 5年を超え10年以下:税率20.315%
- 10年以上:税率10%
ただし、譲渡所得に関しては3,000万円の控除特例である程度免除できます。
そのため、住宅ローン控除を適用する場合やマイホームに買い替えの特例を利用する場合は、5年・10年を目途に住み替えるのがベストでしょう。
確定申告の際に経費を計上する
住み替えの税金は経費として計上することができます。
税金を減らすためにも以下のような料金は経費として計上するようにしましょう。
- 不動産の減価償却費を控除した料金
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 引っ越し費用
- 立退料
他にも経費として計上できる料金はさまざまあります。
不安な方やどれが計上できるか分からないという人は、税理士や会計士などに相談してみると良いでしょう。
住み替えを損せず進めるには「サテイエ」が最適
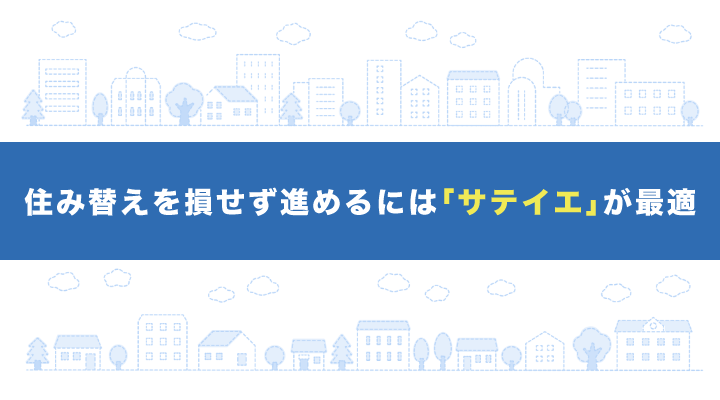
これから住み替えを検討している方は一括査定サイト「サテイエ」の利用をおすすめします。
サテイエでは、物件のタイプや地域、築年数や条件などを考慮した上で、最適な不動産会社を最大6社まで見つけることが可能です。
住み替えで最も重要なのは、不動産会社選びと言っても過言ではありません。
お得に損せず住み替えを完了するためにも、ぜひサテイエを利用して自分に合った不動産会社を見つけてみてください。
まとめ:税金を理解してお得に住み替えよう
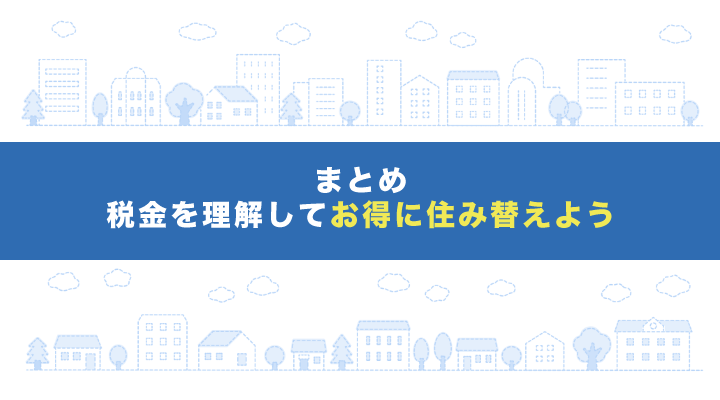
この記事では住み替えにかかる税金について解説しました。
住み替えは不動産の売却・購入を伴うため、高額な税金が発生します。
しかし、その分お得な税金控除なども豊富にあるため、しっかり節税方法を知ることで損せずにお得に住み替えが行えるでしょう。
また、これから住み替えを検討している方は、一括査定サイト「サテイエ」の利用がおすすめです。
自分にぴったりの不動産会社が見つかりますので、ぜひ利用してみてください。
関連記事
-

家を売るには?基礎知識や必要な準備・後悔しないポイントを解説|高く売却する...
2023.02.25
-

お金がないときに家を売る方法を解説|費用や高く売るコツも紹介
2023.03.26
-

家を売る際の4つの注意点を解説|家を売るときNGな注意すべきポイントも紹介
2023.02.25
-

住み替えの税金を総まとめ|節税方法や税金控除の特例も紹介
2023.07.26
-

不動産売却後の確定申告は必要?不要なケースや必要書類などを解説
2022.12.25
-

不動産査定の方法は主に3種類!計算式や査定項目・注意点などを解説
2023.02.25
-

不動産売却における委任状の書き方を解説 | 注意点や必要書類も紹介
2022.12.25
-

不動産売却によって住民税が上がる仕組みを解説|計算方法や翌年の納付時期も紹...
2023.05.23