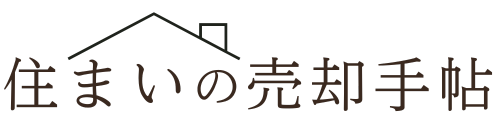相続した不動産を売るときは「売れた金額=手元に残る金額」ではない。
仲介手数料や登記、税金、そして物件状況によっては測量や解体などが重なり、想定より手取りが減ることがある。
一方で、費用の出方には規則性があり、先に全体像を押さえれば見積もりの精度は上げられる。
この記事では、相続不動産の売却で発生しやすい費用を「必ず発生しやすいもの」と「条件で大きく変わるもの」に分けて整理する。
あわせて、費用を抑える実務上の順序と、税金で金額が跳ねる分岐点も具体的に解説する。
相続した不動産売却の費用は仲介手数料が最も大きい

相続不動産の売却費用でまず押さえるべきは仲介手数料である。
多くのケースで、固定費として確実に発生しやすく、金額も他の実費より大きくなりやすいからだ。
仲介手数料を起点に、登記や税金、物件固有の費用を積み上げると見積もりが崩れにくい。
仲介手数料には上限があり交渉の出発点になる
不動産会社に支払う仲介手数料は、上限額の範囲で当事者が合意して決める仕組みである。
上限の考え方は国土交通省の案内に整理されており、媒介契約を結ぶ前に説明を受けておくことが重要だ。
上限の計算は価格帯ごとに料率が定められており、一般に売却価格が高いほど手数料も増える。
根拠の確認は、国土交通省の「不動産取引に関するお知らせ」にある上限表を参照するとよい。
- 仲介手数料は「上限内での合意」が原則である(国土交通省)。
- 媒介契約の締結時に、手数料の上限と計算方法を確認する。
- 上限いっぱいが常に適正とは限らず、サービス範囲とセットで判断する。
800万円以下の不動産は特例で上限の考え方が変わる
売買価格が800万円以下の不動産は、いわゆる「低廉な空き家等」の特例が設けられている。
国土交通省の案内でも、800万円以下のケースは特例があることが明記されており、通常の上限とは別に確認が必要だ。
低価格帯では、調査や広告の固定コストが相対的に重く、不動産会社の報酬体系も変わりやすい。
特例を適用する場合は、説明と合意のプロセスを必ず書面で押さえるとトラブルを減らせる。
| 確認ポイント | 800万円以下に該当するかを媒介契約前に確認する(国土交通省)。 |
|---|---|
| 注意点 | 特例の有無で手数料の説明内容が変わるため、口頭だけで進めない。 |
| 実務のコツ | 「何をしてもらえるのか」を業務範囲として列挙してもらう。 |
売買契約書の印紙税は金額帯で決まる
売買契約書には印紙税がかかり、契約金額の区分に応じて税額が決まる。
税額表は国税庁のタックスアンサーに一覧があり、該当する金額帯を当てはめれば見積もれる。
軽減措置の対象期間や適用条件もあるため、契約書を作成する時点で最新の区分を確認したい。
印紙は「誰が負担するか」が実務上は契約で決めることが多いので、負担者も合わせてチェックする。
- 印紙税額は契約金額の区分で定まる(国税庁)。
- 契約書が複数通なら通数分の印紙が必要になる。
- 電子契約の扱いは契約形態によって異なるため、採用時は専門家に確認する。
相続登記の登録免許税は「不動産の価額×0.4%」が基本
相続した不動産を売るには、通常は名義を相続人へ移す相続登記が前提になる。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、国税庁の税額表で税率が「1,000分の4」と示されている。
課税標準となる不動産の価額は固定資産課税台帳の価格が原則であり、評価の取り方も合わせて押さえる。
免税措置が使える例外もあるため、対象になりそうなら制度要件を先に確認しておくとよい。
抵当権抹消は「不動産1個につき1,000円」が実費として読める
住宅ローンが残っている、または完済済みでも抵当権が残っている場合は、抵当権抹消登記が必要になる。
登録免許税は不動産1個につき1,000円で、土地と建物なら通常2個として2,000円になる。
この点は法務局の案内資料に明記されており、実費部分は比較的見積もりやすい。
自分で申請するか司法書士に依頼するかで、追加負担が大きく変わるので判断材料にしたい。
測量や境界確定は「必要になったら高い」費用である
土地や古家付き土地では、測量や境界確定が必要になると費用がまとまって発生する。
この費用は物件の状況で差が大きく、最初の見積もりから漏れやすい。
買主側の融資審査や重要事項説明の観点で求められることもあり、売却スケジュールにも影響する。
早い段階で不動産会社に「測量が必要になる可能性」を診断してもらうと判断が早くなる。
| 発生しやすい場面 | 境界が不明確な土地、古い分筆履歴がある土地、隣地との越境が疑われる場合である。 |
|---|---|
| 影響 | 費用だけでなく、確定までの期間が売却時期を押すことがある。 |
| 先手 | 現況測量図の有無や境界標の状態を先に確認しておく。 |
解体や残置物処分は「売り方」で要否が変わる
相続した家が老朽化している場合、解体して更地で売るか、現況のまま売るかで費用構造が変わる。
空き家の特例を狙う場合でも、要件の関係で解体や耐震等の条件が絡むことがあるため、税制と売り方をセットで検討したい。
また、残置物処分は家財量で費用が変動しやすく、相見積もりが効きやすい領域である。
売却価格に転嫁できるとは限らないので、手取り計算では保守的に見積もるのが安全だ。
- 「現況渡し」でも残置物の扱いは契約で明確化する。
- 解体の要否は立地と需要で変わるため、査定時に複数パターンで試算する。
- 空き家特例の適用可能性は要件確認が必須である(国税庁)。
譲渡所得税は「売却益」が出たときに最大の負担になり得る
売却で利益が出ると譲渡所得として所得税と住民税がかかり、ここが最も大きな負担になることがある。
所有期間の判定は「売った年の1月1日時点で5年超かどうか」で、税額計算は国税庁が示している。
相続の場合、被相続人の取得時期を引き継ぐため、見た目の保有期間と判定がずれることがある。
税金を見誤ると手取り見込みが大きく崩れるため、早い段階で概算計算を行うべきである。
売却前に必要な手続き費用を見積もる

相続不動産の売却は、売り出す前の「整える段階」で費用が出やすい。
ここを先に押さえると、売却活動中に慌てて出費するリスクが下がる。
名義と権利関係を整え、売却に必要な書類を揃える順序で考えると見積もりが作りやすい。
名義が被相続人のままなら相続登記が起点になる
名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転が進めにくく、実務上は相続登記が起点になる。
登録免許税は相続による所有権移転で税率が定められており、評価額に応じて増減する。
制度として免税措置が設けられている場合もあるため、条件に該当するなら使えるか確認したい。
登記が遅れるほど売却の機会損失が出やすいので、費用だけでなく期限感も意識する。
抵当権の有無を確認し抹消費用を固定費として積む
登記簿で抵当権の有無を確認し、残っているなら抹消登記が必要になる。
登録免許税は不動産1個につき1,000円と明確で、実費として先に積み上げられる。
ローン完済済みでも抹消が未了のまま残っていることがあるため、確認だけで安心しない。
金融機関書類の取り寄せが必要になるので、売却のタイミングに合わせて逆算する。
書類取得の実費は小さいが件数が増えると効いてくる
登記事項証明書や評価証明書、固定資産税納税通知書など、売却に必要な書類は複数ある。
1通あたりの実費は小さくても、相続人が多い、物件が複数ある場合は合計が増える。
書類が足りないと手続きが止まり、結果的に追加コストにつながることがある。
必要書類を不動産会社と司法書士に一覧化してもらい、取得の重複を避けたい。
- 登記と売買の両方で同じ書類が求められることがある。
- 共有者がいる場合は本人確認書類の準備にも時間と費用がかかる。
- 郵送取り寄せは日数がかかるため、手数料より機会損失が大きくなりやすい。
境界や越境の不安があるなら調査費を先に見込む
境界が曖昧な土地は、売買の段階で買主から追加資料を求められやすい。
測量や境界確認は、費用だけでなく確定までの時間が売却の足かせになる。
先に現地を見てもらい、測量が不要なパターンかどうかを切り分けるだけでも有益である。
必要になった場合の費用レンジは物件でブレるため、見積もりは複数社で取ると精度が上がる。
| 判断材料 | 境界標の有無、隣地との位置関係、過去の確定測量図の有無である。 |
|---|---|
| 影響 | 売却時期が延びると、固定資産税や管理費の負担が増える。 |
| 対策 | 売却活動前に「必要なら実施」の判断を下せる状態にする。 |
売却活動で発生する費用を抑えるコツ

売却活動に入ると、広告費や内覧対応など「見えにくいコスト」が出てくる。
ただし多くは、仲介手数料の範囲内の業務として含まれるため、契約段階の設計が鍵になる。
費用を抑えるというより、不要な追加請求を避けるための確認が重要だ。
媒介契約の種類で販売戦略とコスト感が変わる
媒介契約には複数の形があり、情報公開の範囲や報告義務が変わる。
費用面では、仲介手数料の上限自体は変わらなくても、販売活動の手厚さが変わることがある。
売却期間が伸びると維持費が積み上がるため、費用は「手数料」だけで見ないことが大切だ。
自分に合う販売戦略を合意するためにも、上限の考え方を先に理解しておく。
- 仲介手数料は上限内で合意する仕組みである(国土交通省)。
- 販売期間が延びると固定資産税や管理費がコスト化する。
- 報告頻度と広告方針を契約前に言語化する。
追加費用が発生しやすい項目を契約書で線引きする
「広告費」「現地看板」「遠方立会い」などは、契約条件次第で追加負担になることがある。
トラブルを避けるには、追加費用が発生する条件と金額上限を契約時に明記することが有効だ。
上限内での合意という原則があるからこそ、例外を曖昧にしない姿勢が重要になる。
不明点は、国土交通省が示す仲介手数料の考え方を踏まえて質問すると通りやすい。
| 線引き例 | 通常広告は手数料内、特別広告は事前承諾が必要などである。 |
|---|---|
| 確認の根拠 | 上限内で合意する考え方を確認する(国土交通省)。 |
| 実務のコツ | 「追加請求の可能性がある項目」を箇条書きで出してもらう。 |
残置物と設備不具合は「引渡し条件」で費用が変わる
残置物処分や設備の不具合対応は、売主がどこまで負担するかで費用が変わる。
現況渡しであっても、契約不適合責任の扱いは条項で整理されるため、理解不足はリスクになる。
売主負担が増えるほど手取りは減るので、条件交渉は価格だけでなく費用面でも見るべきだ。
判断に迷う場合は、売却価格への影響とセットで不動産会社に比較表を作ってもらう。
- 「現況渡し」の範囲を具体化しないと後から費用負担が生じやすい。
- 付帯設備表の記載でトラブルの芽を減らせる。
- 処分費は相見積もりの効果が出やすい。
一括査定は「価格」より「費用の見積もり精度」を見比べる
査定を複数取るときは、査定額の上下だけで判断すると失敗しやすい。
相続登記や抵当権抹消、印紙税などの必須費用をどれだけ具体に積んでくれるかが重要になる。
さらに、境界や解体が必要になりそうかというリスク評価があると、費用ブレが小さくなる。
査定依頼時点で「費用の内訳テンプレ」を渡し、同じ粒度で返してもらうと比較がしやすい。
税金で金額が跳ねる場面

相続不動産の売却では、税金の見立てが手取りを最も左右しやすい。
とくに譲渡所得税は、取得費の扱いと特例の適用可否で大きく変わる。
「節税できるか」より先に「課税されるか」を見極めることが現実的である。
所有期間の判定は被相続人の取得時期を引き継ぐ
譲渡所得が長期か短期かは、売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで決まる。
相続では被相続人の取得時期を引き継ぐため、相続して間もない売却でも長期扱いになることがある。
国税庁は相続による取得時期の引継ぎを示しており、ここを誤ると税率の想定がずれる。
まずは取得日が分かる資料を集め、概算でも区分を確定させることが第一歩だ。
取得費が不明だと「売却額の5%」扱いになり税負担が増えやすい
譲渡所得は、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
相続した土地建物の取得費は被相続人の購入代金等を基にするのが原則で、国税庁が考え方を示している。
取得費が分からない場合に売却額の5%相当を取得費とする方法もあるが、結果として利益が大きく見えて税負担が増えやすい。
可能な限り売買契約書や領収書を探し、取得費を厚くできるかを検討したい。
相続税を払っているなら取得費加算の特例が効くことがある
相続税が課税されている場合、一定要件のもとで相続税額の一部を取得費に加算できる特例がある。
国税庁は要件として、相続税が課税されていることや、一定期間内の譲渡であることを示している。
同じ売却額でも課税譲渡所得が下がれば、譲渡所得税の負担を抑えられる可能性がある。
相続税申告書や納税額の資料が必要になるため、売却準備と並行して整えておくとよい。
空き家の3,000万円特別控除は要件が細かいので早期判定が必須
被相続人の居住用財産に該当する空き家を一定期間内に売る場合、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられる制度がある。
国税庁は制度の概要と期間、そして相続人が3人以上の場合の控除額の扱いなどを示している。
適用できれば税負担が大きく変わる一方、要件を満たさないとゼロになるため、期待だけで進めるのは危険だ。
売却の意思決定をする前に、物件が制度の対象かをチェックリスト形式で確認すると判断が早い。
費用トラブルを避けるためのチェックポイント

相続不動産の売却は、関係者と書類が増えるため、費用トラブルが起きやすい。
よくある原因は「誰が払うのかが曖昧」「費用の発生条件が曖昧」「税金の見込みが甘い」の三つである。
契約と事前確認で防げるものが多いので、型を決めて進めるとよい。
費用負担者は契約で決めるものが多い
印紙税や各種手続き実費は、慣行で決まることもあるが、最終的には契約で整理される。
「売主が当然に払う」と思い込むと、想定外の支出で揉めることがある。
契約書と重要事項説明で、費用負担の条項を必ず確認する習慣が大切だ。
迷う項目は、契約書に明記できるよう言葉に落として質問する。
- 印紙税は契約書に貼付する税であり、通数と負担者を確認する(国税庁)。
- 残置物や修繕の負担は引渡し条件とセットで決める。
- 口頭合意は後で崩れやすいので書面化する。
見積書は「発生条件」と「上限」をセットで集める
解体、測量、残置物処分などの変動費は、見積書の取り方で差が出る。
金額だけでなく、何が含まれて何が含まれないかを発生条件として明確にすることが重要だ。
追加工事が起こり得る項目は、上限または追加単価のルールを確認する。
複数社比較のときは、同じ前提条件を揃えるとブレが小さくなる。
| 最低限そろえる | 作業範囲、追加条件、見積有効期限、支払条件である。 |
|---|---|
| 上限の考え方 | 仲介手数料は上限内での合意が基本である(国土交通省)。 |
| 実務 | 比較表を作り、合計費用だけでなくリスクも並べる。 |
税金の概算は「取得費」と「特例候補」の2点で早めに当てる
譲渡所得税の概算は、取得費の有無と特例の候補で大枠が決まる。
国税庁は取得費の考え方や、取得費加算の特例、空き家の特例などを個別に示している。
売却活動を始めてから税金を計算すると、条件変更が難しくなり手取りが固まりやすい。
税理士費用がかかるとしても、結果的に手取りと意思決定の質が上がることが多い。
登記の実費は読めるので「専門家報酬」と切り分ける
登録免許税のような法定実費は比較的読めるため、見積もりは崩れにくい。
一方で司法書士や税理士の報酬は依頼範囲で変わるため、ここを曖昧にすると総額が読めなくなる。
実費と報酬を分け、どこまでを委託するかを先に決めると費用管理がしやすい。
抵当権抹消の登録免許税のように根拠が明確な項目は、資料で確認してから積み上げる。
| 実費の例 | 抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円(法務局PDF)。 |
|---|---|
| 税率の例 | 相続による所有権移転登記は1,000分の4(国税庁)。 |
| 報酬の扱い | 依頼範囲を決め、見積書で「何をするか」を明確化する。 |
費用の全体像を把握して相続不動産の売却を進めよう

相続した不動産売却の費用は、仲介手数料を中心に、登記と税金、そして物件状況で変わる費用が重なって決まる。
まずは国土交通省の上限表で仲介手数料の枠を確認し、国税庁の税額表やタックスアンサーで印紙税と登録免許税の実費を積む。
次に、取得費の根拠資料と特例候補を整理して譲渡所得税の概算を当てると、手取りのブレが小さくなる。
最後に、測量や解体などの変動費は「必要になる条件」を先に判定し、見積もりの前提を揃えて比較する。
この順序で進めれば、費用の不安に振り回されず、納得感のある売却判断ができる。