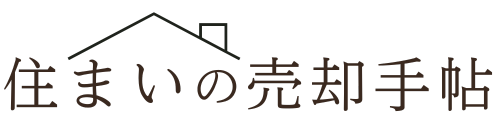不動産を売ったときの「売却益」は、感覚ではなく計算式で決まります。
売却価格だけを見ていると、取得費や売却のための費用が抜けて、税金が想定より増えることがあります。
この記事は、譲渡所得の基本式から、取得費の集め方、税率、特例までを一つの流れで整理します。
国税庁の一次情報に沿って、手元の資料に当てはめるだけで数字を出せる構成にします。
不動産売却益の計算方法は「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)」

不動産の売却益は「譲渡所得」として、売却価格から取得費と譲渡費用を引いて計算します。
国税庁も、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引く計算を示しています(国税庁 No.3202)。
まずは式を固定し、次に各項目へ何を入れるかを決めると迷いません。
最初に用意する3つの数字
計算に必要なのは、売却価格、取得費、譲渡費用の3つです。
この3つが揃えば、売却益の大枠はその場で出せます。
売却価格は契約書の金額、取得費は買ったときの総コスト、譲渡費用は売るために直接かかった費用です。
数字が曖昧な項目があるときは、後述の「概算取得費」や「費用の可否判定」で補います。
売却益の計算を早く終わらせるコツは、領収書を探す前に「項目リスト」を作って抜けを可視化することです。
- 売却価格(収入金額)
- 取得費(購入代金、購入手数料、改良費など)
- 譲渡費用(仲介手数料、測量費、印紙代など)
- 建物の減価償却控除の有無
- 特別控除や軽減税率の適用可否
- 所有期間の判定日(売った年の1月1日)
- 申告に使う書類の所在
売却価格に入る金額の考え方
売却価格は、基本的に売買契約書に記載された譲渡価額を使います。
土地と建物を一括で売った場合は、契約書の配分や固定資産税評価などを参考に按分する場面があります。
代金の一部を修繕負担や設備代として別立てにすると、税務上の扱いが変わることがあるため注意が必要です。
迷ったときは、契約書に書かれた名目ごとに「対価か、費用の精算か」を区別して整理します。
収入金額の基本は「売った金額」である点を押さえておくと、式が崩れません。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 売買代金 | 原則として収入金額 |
| 手付金 | 最終的に売買代金に含めて整理 |
| 固定資産税等の精算金 | 精算の性質を確認して整理 |
| 設備の対価 | 契約書の記載に沿って按分検討 |
| 違約金の受領 | 契約関係により扱いが変わる |
取得費に入るものを先に確定する
取得費は、買ったときの購入代金や購入手数料など「取得に要した金額」に、改良費や設備費を加えた合計です。
国税庁も、購入代金や購入手数料に改良費等を加える考え方を示しています(国税庁 No.3202)。
建物部分がある場合は、取得費から減価償却相当額を差し引く点が重要です。
取得費は「買った瞬間の支出」だけでなく、その後の価値を高める支出まで含むのがポイントです。
固定資産税や火災保険など、維持のための支出は原則として取得費に入れにくいので分けて管理します。
- 購入代金・建築代金
- 購入時の仲介手数料
- 登録免許税や司法書士報酬など取得に伴う費用
- 不動産取得税(取得に伴う税負担として整理)
- 増改築、リフォームのうち改良費に当たるもの
- 設備の増設や造成など価値を上げる支出
- 測量や境界確定のうち取得時に直接必要なもの
建物の取得費は減価償却分を差し引く
建物の取得費は、購入代金や建築代金の合計から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
国税庁も、建物は減価償却費相当額を差し引くことを明示しています(国税庁 No.3252)。
自宅でも建物は年数で価値が減る前提のため、取得費が想定より下がりやすい点に注意が必要です。
賃貸にしていた期間がある場合は、減価償却の計算が複雑になるため、数字の根拠を残すことが重要です。
計算が難しいと感じたら、まずは建物価格と構造、築年、用途の情報を整理すると前に進みます。
| 確認項目 | メモ |
|---|---|
| 土地と建物の按分 | 契約書や評価額で整理 |
| 建物の構造 | 木造、鉄骨、RCなど |
| 取得日と売却日 | 所有期間と償却期間に影響 |
| 居住か賃貸か | 扱いが変わる場面がある |
| 償却相当額 | 取得費から控除して計算 |
取得費が分からないときは概算取得費5%を使える
古い不動産で契約書が見つからない場合など、取得費が分からないことがあります。
その場合、売った金額の5%相当額を取得費とする「概算取得費」を使えると国税庁が示しています(国税庁 No.3258)。
また、実際の取得費が売却価額の5%を下回るときも、5%を取得費にできる場合があります。
概算取得費は便利ですが、実額より小さくなりやすく、課税所得が増える方向に働きやすい点に注意が必要です。
後から実額を立証できる資料が出てくると結果が変わるため、まずは資料探索を尽くしたうえで最終手段として使います。
- 取得費不明のときに使える
- 売却価額の5%を取得費にできる
- 実額が5%未満でも5%を使える場合がある
- 実額が大きいほど課税所得は減りやすい
- 資料探索の優先順位を決めてから判断する
- 相続・贈与の場合は別の注意点がある
譲渡費用にできる支出とできない支出
譲渡費用は「売るために直接かかった費用」で、仲介手数料や測量費などが代表例です。
国税庁は、仲介手数料、売主負担の印紙税、立退料、取壊し費用などを譲渡費用の例として挙げています(国税庁 No.3255)。
一方で、修繕費や固定資産税など維持管理の費用は譲渡費用にならない旨も示されています。
「売却のために直接必要だったか」を一つずつ判定すると、費用計上の精度が上がります。
領収書がない場合でも、契約書や請求書、振込明細が証拠になり得るので、合わせて保管します。
| 分類 | 代表例 |
|---|---|
| 譲渡費用になりやすい | 仲介手数料、測量費、印紙代、立退料 |
| 条件付きで判断 | 解体費用、違約金、名義書換料 |
| 原則なりにくい | 修繕費、固定資産税、火災保険料 |
| 証拠の形 | 領収書、請求書、契約書、振込明細 |
計算例で売却益を最後まで出す
式に数字を当てはめると、売却益は手順どおりに出せます。
国税庁の基本式は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」である点を前提にします(国税庁 No.3202)。
ここでは計算の形を固定し、あなたの数字に置き換えられるようにします。
実務では、土地建物の按分や建物の償却が絡むため、まずは概算で全体像を掴むのが有効です。
概算が出たら、取得費と譲渡費用を精査して精度を上げる流れが最短です。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 売却価格 | 4,000万円 |
| 取得費 | 2,800万円 |
| 譲渡費用 | 200万円 |
| 譲渡所得(売却益) | 4,000万円-(2,800万円+200万円)=1,000万円 |
売却益にかかる税金は所有期間で大きく変わる

売却益が出たら、次は「どの税率がかかるか」を判定します。
税率は所有期間で変わり、同じ売却益でも納税額が大きく変わります。
所有期間の判定基準は、売却日ではなく「売った年の1月1日」である点が重要です(国税庁 No.3202)。
所有期間は「売った年の1月1日」で判定する
長期譲渡所得か短期譲渡所得かは、譲渡した年の1月1日における所有期間で決まります。
5年を超えると長期、5年以下だと短期として扱われます(国税庁 No.3202)。
たとえば「取得から5年を少し超えた」つもりでも、1月1日時点で5年以下なら短期になることがあります。
境目の年は、売却のタイミングで税率が跳ねるため、契約日と引渡日を含めて早めに確認します。
判定を間違えると申告後の修正が必要になるので、取得日を示す資料もセットで保管します。
- 判定日は売却日ではない
- 基準は譲渡年の1月1日
- 5年超は長期譲渡所得
- 5年以下は短期譲渡所得
- 境目の年は特に注意
- 取得日資料は必ず残す
長期譲渡所得の税率と内訳
長期譲渡所得の税額は、課税長期譲渡所得金額に税率を掛けて計算します。
国税庁は所得税15%と住民税5%を示しており、復興特別所得税が上乗せされます(国税庁 No.3208)。
復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告納付する仕組みです(国税庁 No.3208)。
結果として、長期の合計税率は20.315%として説明されることが多いです。
税率は「売却益」ではなく「課税譲渡所得」に掛かるため、特別控除の後で計算します。
| 区分 | 税率の目安 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 所得税額×2.1% |
| 住民税 | 5% |
| 合計イメージ | 20.315%程度 |
短期譲渡所得の税率と内訳
短期譲渡所得は、長期に比べて税率が高く設定されています。
国税庁は所得税30%と住民税9%を示しており、復興特別所得税が上乗せされます(国税庁 No.3211)。
復興特別所得税の仕組みは長期と同様に、基準所得税額の2.1%です(国税庁 No.3211)。
短期の合計税率は39.63%として整理され、利益に対する負担感が大きくなります。
短期になる可能性があるなら、売却時期の調整や特例適用の有無を早い段階で検討します。
| 区分 | 税率の目安 |
|---|---|
| 所得税 | 30% |
| 復興特別所得税 | 所得税額×2.1% |
| 住民税 | 9% |
| 合計イメージ | 39.63%程度 |
税金の見積もりで見落としやすいポイント
税率を掛ける対象は、取得費と譲渡費用を引いた後の譲渡所得です。
さらに特別控除がある場合は、控除後の「課税譲渡所得」に税率を掛けます。
この順序を逆にすると、税額が大きくズレます。
また、手取りの試算では仲介手数料や印紙代などのキャッシュアウトも合わせて整理します。
税金とキャッシュフローを同じ表に並べると、売却後に残る金額が見えやすくなります。
- 税率は課税譲渡所得に掛ける
- 特別控除の後で税額計算
- 所有期間で税率が変わる
- 費用と税金は別に管理する
- 手取りはキャッシュベースで確認
- 境目の年は早めに試算
マイホーム売却は3,000万円特別控除で課税がゼロになることがある

居住用財産を売った場合は、一定の要件で3,000万円の特別控除が使えます。
控除が効くと、売却益が出ていても税金がゼロになるケースがあります。
国税庁は、マイホーム売却で譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を示しています(国税庁 No.3302)。
3,000万円特別控除で減らせる金額
3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引く制度です。
譲渡所得が3,000万円未満なら、その譲渡所得が限度になり、課税譲渡所得がゼロになります(国税庁 No.3302)。
譲渡所得が3,000万円を超える場合は、超えた部分に税率が掛かります。
特別控除は「税額から引く」のではなく「課税対象の利益から引く」ため、効果が大きいのが特徴です。
まずは売却益を計算し、その後に特別控除を当てて税率計算に進みます。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 2,500万円 |
| 特別控除 | 2,500万円(上限3,000万円の範囲) |
| 課税譲渡所得 | 0円 |
| 税額イメージ | 0円(他の要件も満たす前提) |
適用できるマイホームの範囲を整理する
対象は「居住用財産」としてのマイホームで、一定の要件を満たす必要があります。
国税庁の特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除として整理されています(国税庁 No.3302)。
住まなくなった後に売る場合でも、期限や条件が絡むため、売却までの年数を確認します。
親子や夫婦など特別な関係者への売却では適用できないことがあるため、相手方の関係も要確認です。
特例の可否が微妙なら、契約前に税理士へ相談して要件を潰しておくと安全です。
- 居住用財産(マイホーム)が対象
- 住まなくなってから売る場合は期限確認
- 同一年の他の特例との関係を確認
- 特別関係者への売却は注意
- 売却前に要件チェックを行う
- 確定申告が必要になる
10年超の軽減税率が使えるケース
所有期間が10年を超えるマイホーム売却では、長期譲渡所得を通常より低い税率で計算できる制度があります。
国税庁は「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を示しており、一定の要件で適用できるとしています(国税庁 No.3305)。
この軽減税率は、3,000万円特別控除と併用できる場面があり、超過部分の税負担を抑える考え方になります。
適用には細かな要件があるため、所有期間だけで決め打ちせずチェックシート等で確認します。
まずは3,000万円控除を当て、その後に軽減税率を当てる順序で考えると整理しやすいです。
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 対象 | 10年超の居住用財産(要件あり) |
| 効果 | 長期譲渡所得を軽減税率で計算 |
| 併用 | 3,000万円控除と併用できる場面がある |
| 確認先 | 国税庁 No.3305 |
特例を使うときの申告イメージ
特例を使う場合でも、確定申告をしなければ控除や軽減が反映されません。
申告では、譲渡所得の内訳書など、売却内容を示す書類を添付して計算根拠を示します。
国税庁の手引きPDFでも、居住用財産の特例に関する添付書類が整理されています(国税庁 申告の手引き(譲渡))。
書類は「取得費」「譲渡費用」「所有期間」「居住の事実」を示すものが中心になります。
売却した翌年の申告期限を逆算して、契約時点から書類を一箇所にまとめておくと楽です。
- 確定申告をしないと特例が反映されない
- 譲渡所得の内訳書を作成する
- 売買契約書や登記事項証明書を用意する
- 住民票や戸籍の附票が必要になることがある
- 領収書は取得費と譲渡費用で分ける
- 期限から逆算して準備する
相続や古い不動産は取得費の集め方が結果を左右する

相続や取得時期が古い不動産は、取得費の資料が散逸しやすいのが現実です。
取得費が小さくなるほど課税所得が増えるため、資料の集め方で税額が変わります。
国税庁も、取得費が分からない場合の扱いや、相続で取得した場合の考え方を整理しています。
売買契約書がないときの調べ方
契約書が見つからなくても、取得費を推定できる資料は複数あります。
登記の原因日や金融機関の融資資料、当時の重要事項説明書が手がかりになります。
固定資産税の課税明細や評価証明は、按分や時点確認に役立ちます。
それでも取得費が確定できない場合は、概算取得費5%を検討します(国税庁 No.3258)。
優先順位を決めて探すと、途中で手が止まらずに済みます。
- 登記事項証明書で取得時期を確認
- 金融機関の融資契約書や返済予定表
- 重要事項説明書や分譲時パンフレット
- 当時の仲介手数料の請求書
- リフォームや増改築の契約書
- 固定資産税の課税明細で按分検討
- 見つからない場合は概算取得費を検討
相続や贈与で取得した不動産の取得費
相続や贈与で取得した土地建物を売った場合の取得費は、原則として被相続人や贈与者の取得費を引き継ぎます。
国税庁も、被相続人等が買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算する旨を示しています(国税庁 No.3270)。
相続時に相続人が支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含められるケースも示されています(国税庁 No.3270)。
ただし、取得費が不明で概算取得費を使う場合は、登記費用等を取得費に含められない点にも注意が必要です(国税庁 No.3270)。
相続は資料が複数人に分散しやすいので、早めに共有フォルダ等へ集約すると失念を防げます。
| 論点 | 国税庁の整理 |
|---|---|
| 取得費の基礎 | 被相続人等の購入代金等を基に計算 |
| 相続人の登記費用 | 取得費に含められる場合がある |
| 概算取得費を使う場合 | 登記費用等を含められない注意 |
| 確認先 | 国税庁 No.3270 |
相続税を払っているなら取得費加算の特例を検討する
相続や遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。
国税庁は、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる旨を示しています(国税庁 No.3267)。
要件には「相続税が課税されていること」や「一定期間内の譲渡」が含まれます(国税庁 No.3267)。
取得費に加算できれば譲渡所得が減るため、結果的に譲渡所得税の負担を抑えられます。
相続税の申告書や納税額の資料が必要になるため、相続手続きの書類も一緒に管理します。
- 相続税が課税されていることが前提
- 一定期間内に譲渡していることが必要
- 相続税額の一部を取得費に加算できる
- 譲渡所得が減り税負担が下がりやすい
- 相続税申告書や納税資料が必要
- 対象財産と税額の対応関係を整理する
相続不動産の所有期間の数え方
税率区分に直結する所有期間は、相続の場合も重要です。
相続で取得したときは、被相続人の取得時期が相続人に引き継がれると国税庁は示しています(国税庁 No.3270)。
つまり、相続してすぐ売っても、被相続人が長く保有していれば長期になる可能性があります。
逆に、被相続人の取得から5年以内なら短期になる可能性もあるため、取得時期の確認が必須です。
所有期間の判定基準は売却年の1月1日である点も合わせて当てはめます(国税庁 No.3202)。
| 確認項目 | 見るべき資料 |
|---|---|
| 被相続人の取得日 | 古い売買契約書、登記原因日 |
| 相続発生日 | 戸籍、相続関係説明図 |
| 売却年の基準日 | 1月1日で判定 |
| 税率区分 | 5年超か5年以下か |
譲渡損失が出たときは損益通算できるケースがある

売却益が出るとは限らず、計算すると損失になるケースもあります。
損失の扱いは原則が厳しく、どの所得と相殺できるかがポイントです。
国税庁は、譲渡損失の基本的な扱いと、居住用財産で一定の場合に損益通算できる例外を示しています(国税庁 No.3203)。
原則は給与所得などと損益通算できない
土地や建物の譲渡で損失が出ても、原則として給与所得など他の所得と損益通算はできません。
国税庁は、控除しきれない損失を事業所得や給与所得などと損益通算できない旨を示しています(国税庁 No.3203)。
ただし、同じ年の他の土地建物の譲渡所得があれば、その中で控除できる余地があります。
まずは「他に譲渡所得があるか」を確認し、同一年内での相殺を整理します。
損失が出た場合でも、確定申告で計算を確定させないと次の判断に進めません。
| 状況 | 原則の扱い |
|---|---|
| 土地建物の譲渡損失 | 他の譲渡所得と相殺は可能 |
| 控除しきれない損失 | 給与所得等との通算は原則不可 |
| 確認先 | 国税庁 No.3203 |
マイホームの買換え等なら損益通算と繰越ができる
居住用財産の買換えなど一定のケースでは、例外的に損益通算が認められることがあります。
国税庁は、マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき、一定要件で給与所得等から控除できる旨を示しています(国税庁 No.3370)。
さらに、控除しきれない損失は翌年以後3年内に繰り越して控除できるとされています(国税庁 No.3370)。
損失でも特例の要件判定があるため、自己判断せず条件を一つずつ確認します。
買換えの有無や入居時期など生活実態の証拠が必要になるので、住民票や契約書類を残します。
- 買換え等の特例に該当するか確認
- 要件を満たせば給与所得等と損益通算
- 控除しきれない損失は3年繰越があり得る
- 売買契約書と入居の資料を保存
- 年をまたぐため申告スケジュールが重要
- 迷う場合は税理士へ相談
損失の有無に関わらず申告で必要になる書類
利益でも損失でも、譲渡所得の計算を示す書類が必要です。
特例を使う場合は、さらに登記事項証明書や住民票関係などの添付が求められます。
国税庁の手引きには、居住用財産の特例で必要となる書類が整理されています(国税庁 申告の手引き(譲渡))。
必要書類を「取得費」「譲渡費用」「特例要件」の3箱に分けると、作業が分解されてスムーズです。
提出前に不足が見つかると期限が厳しくなるため、契約直後から集めるのが安全です。
| 分類 | 代表的な書類 |
|---|---|
| 売却の証拠 | 売買契約書、決済書類 |
| 取得費の証拠 | 購入契約書、領収書、リフォーム契約書 |
| 譲渡費用の証拠 | 仲介手数料領収書、測量費請求書、印紙代 |
| 特例の証拠 | 登記事項証明書、住民票、戸籍の附票など |
譲渡損失の判断で間違えやすい落とし穴
損失かどうかは「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で決まります。
取得費の資料が不足して概算取得費5%で計算すると、損失が利益に変わることがあります。
建物の減価償却控除を入れ忘れると、取得費が過大になって損失と誤判定することがあります。
また、譲渡費用にできない維持費を混ぜると、損失が膨らんで見えるため判定がブレます(国税庁 No.3255)。
結論を急がず、取得費と費用の根拠が揃ってから損益通算の可否判定に進みます。
- 概算取得費で損益が変わりやすい
- 減価償却控除の入れ忘れに注意
- 譲渡費用にできない維持費を除外
- 資料が出るまで暫定計算でよい
- 要件判定はチェックリスト化する
- 不安なら早めに専門家へ確認
売却益計算は資料集めから逆算すると迷わない

不動産売却益の計算は、式そのものより「何を根拠に入れるか」で詰まりやすい作業です。
売却価格、取得費、譲渡費用をそれぞれ証拠資料に紐づけ、所有期間と特例の可否を最後に判定すると整います。
国税庁の一次情報で計算の骨格を固定し、概算と実額の二段階で精度を上げると、申告直前に慌てません(国税庁 No.3202)。
境目の年や相続案件など判断が分かれるときは、早めに試算して選択肢を残すのが安全です。
最終的に残るお金を把握するには、税金と費用を同じ一覧で見える化し、手取りをキャッシュで確認してください。