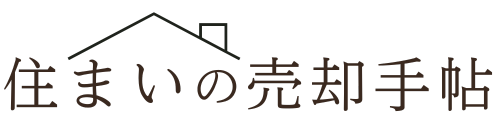法人で不動産を売却すると「譲渡所得の税率は何%なのか」「個人と同じ分離課税なのか」といった疑問が一気に出てきます。
結論から言うと、法人の不動産売却益は原則として法人の所得に合算され、法人税等(国税と地方税の合計)として課税されます。
そのため「不動産だから〇年超は〇%」のような個人の譲渡所得の発想をそのまま当てはめると、税額の見積りを外しやすいです。
この記事では、税率の目安を示したうえで、売却益の計算、消費税、印紙税、会計処理、実務のチェックポイントまでを一続きで整理します。
法人の不動産売却の税率は実効30%前後が目安

法人の不動産売却益は法人税等の対象になり、実効ベースで30%前後を起点に考えると見積りが安定します。
最初に押さえる税率イメージ
法人の不動産売却益は、原則として他の事業利益と合算して課税されます。
そのため税率は「法人税率だけ」ではなく、地方法人税や法人住民税、法人事業税などの合計で考える必要があります。
実務では、所在地や資本金規模などで上下しますが、まずは実効30%前後を出発点にすると検討が進みます。
- 起点の目安:実効30%前後
- 上振れ要因:超過税率や外形標準課税の影響
- 下振れ要因:繰越欠損金の控除や売却損との相殺
個人の譲渡所得と同じ計算だとズレる場面
個人の不動産売却は、譲渡所得として分離課税が論点になりやすいです。
一方で法人は、譲渡益も損も原則として法人所得に合算される点が大きな違いです。
「長期・短期で税率が変わる」という整理は、法人の売却益そのものには基本的に当てはまりません。
| 比較点 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 課税の考え方 | 所得に合算 | 譲渡所得で分離課税が多い |
| 税率の見方 | 法人税等の実効税率 | 短期・長期などの区分が重要 |
| 特例の傾向 | 個人向け特例は原則使えない | 居住用などの特例がある |
税率が会社ごとに変わる主な理由
法人税等は複数の税目の合算で、会社の条件によって構成が変わります。
たとえば資本金や所得金額により、法人税率の区分や地方税の税率区分が変わることがあります。
また都道府県によって超過税率の有無が異なるため、同じ利益でも税額が揺れます。
- 資本金規模と中小法人区分
- 所得金額レンジによる税率区分
- 所在地の超過税率と外形標準課税
- 欠損金の有無と相殺可能性
2026年4月以後開始事業年度は防衛特別法人税も意識する
令和7年度税制改正では、防衛特別法人税の仕組みが示されています。
概要としては、課税標準法人税額に一定税率を乗じる付加税の形で整理されます。
適用時期は「2026年4月1日以後に開始する事業年度」が基準なので、自社の事業年度開始日に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用開始 | 2026年4月1日以後開始事業年度 |
| 計算の枠組み | 課税標準法人税額に税率を乗じて算定 |
| 基礎控除の考え方 | 基準法人税額から基礎控除額を控除する設計 |
| 根拠 | 財務省 令和7年度税制改正の大綱/国税庁リーフレット |
税率以外に手取りを左右するコスト
税率を押さえても、手取りはコストの入り方で大きく変わります。
特に法人は、帳簿価額や解体費、測量費、仲介手数料などが損金や取得費の論点として効いてきます。
見積りの段階から「どの費用がどこに入るか」を決めておくと、税額のブレが減ります。
- 仲介手数料と広告費
- 測量費と境界確定費用
- 解体費や立退料の位置づけ
- 登記関連費用と司法書士報酬
法人の不動産売却益が課税される仕組み

法人の不動産売却は「売却益をどう計算して、どの所得として申告するか」を理解すると税率の話が一気につながります。
売却益は原則として法人所得に合算される
法人が事業用資産として保有していた土地建物を売却すると、売却益は法人の所得計算に取り込まれます。
つまり「その期の利益が増える」ほど法人税等の課税ベースも増える構造です。
反対に売却損が出れば、他の黒字と相殺して税負担を減らす方向に働きます。
- 売却益は原則として益金
- 売却損は原則として損金
- 黒字と赤字の相殺で納税額が変動
売却益の基本計算を式で固定する
売却益の計算は、まず式を固定してから、各要素の範囲を詰めるのが近道です。
個別の扱いはありますが、骨格は「譲渡収入から帳簿価額や譲渡費用を控除する」という考え方になります。
この時点で、どの費用を譲渡費用に含めるかの整理が重要になります。
| 要素 | 内容の例 |
|---|---|
| 譲渡収入 | 売買代金、精算金など |
| 帳簿価額 | 取得原価から減価償却累計額を控除した残高 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、測量費、立退料など |
| 売却益 | 譲渡収入-帳簿価額-譲渡費用 |
減価償却後の帳簿価額が税額を動かす
建物は減価償却を行うため、長期保有ほど帳簿価額が下がりやすいです。
帳簿価額が小さいほど売却益が大きく出やすく、税負担が増える方向に働きます。
売却前に固定資産台帳で残高を確認しておくと、想定外の利益計上を防げます。
- 建物は減価償却で帳簿価額が減る
- 帳簿価額が低いほど売却益が増えやすい
- 償却方法や耐用年数の前提を再確認
売却損が出る場合の扱いも同時に確認する
売却損が出た場合は、その期の法人所得を圧縮する効果が期待できます。
ただし取引の合理性が弱いと、寄附金認定や時価評価の論点が出る場面があります。
価格設定や契約条件は、第三者間取引として説明できる形で整えておくと安全です。
| ケース | 実務上の留意点 |
|---|---|
| 第三者に売却損 | 原則として損金になりやすい |
| 関係会社に安価譲渡 | 時価や移転価格の説明が必要 |
| 役員や株主に譲渡 | 利益供与とみられない設計が重要 |
| 特殊条項が多い契約 | 実質価額の説明資料を残す |
法人税率そのものは何%なのか

法人の不動産売却で「税率」を語る場合、まず法人税率の区分を押さえたうえで、地方税を合算して実効税率に落とし込みます。
法人税率は区分で変わる
法人税率は、普通法人かどうか、資本金規模などで区分されます。
資本金1億円以下の法人などには、一定の所得金額まで軽減税率が用意されています。
税率表は国税庁の整理が最も確実なので、判断に迷う場合は原典に当たるのが安全です。
| 区分 | 税率の例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 中小法人の年800万円以下部分 | 15% | 国税庁 No.5759 |
| 上記以外の普通法人 | 23.2% | 国税庁 No.5759 |
| 税制改正による特例の注意 | 条件により別税率 | 国税庁 改正概要PDF |
中小法人の軽減税率は条件を満たす必要がある
軽減税率は自動で適用されるわけではなく、区分判定が前提です。
代表的な判定軸として資本金規模があり、グループ関係や適用除外の論点も絡みます。
売却益が大きい年ほど影響額も大きいので、決算前に税区分の確認をしておくと安心です。
- 資本金1億円以下かどうか
- 適用除外事業者に該当しないか
- 所得金額のうち年800万円以下部分の位置づけ
地方税を含めた実効税率で見積もる
法人税だけを見て税額を出すと、最終納税額と乖離します。
法人の所得には、法人税のほかに地方法人税や法人住民税、法人事業税などがかかるためです。
法定実効税率の例として、東京都のケースで具体的な数値が示されています。
| 観点 | 要点 | 参考 |
|---|---|---|
| 実効税率の意味 | 法人税等の合計負担率 | みずほ銀行 解説 |
| 東京都の例 | 法定実効税率30.62%などの例示 | マネーフォワード解説 |
| 地方税の判定 | 税率区分は所在地等で変動 | 東京都主税局 |
実効税率をざっくり見積もる手順
最初は正確さよりも、意思決定に足りる精度でスピーディに見積もることが重要です。
次に、前提のズレが出やすい論点だけを上書きして精度を上げます。
この手順にすると、税理士確認の前でも社内で説明しやすい見積書になります。
- 売却益を概算し、課税所得の増分を出す
- 所在地と規模から実効税率レンジを決める
- 消費税や印紙税など別建てコストを足す
- 最終的に手取りと資金繰りへ落とし込む
不動産売却で見落としやすい消費税と印紙税

法人の不動産売却は法人税等だけでなく、消費税や印紙税が絡むため、契約形態によって総コストが変わります。
土地は非課税で建物は課税になりやすい
土地の譲渡は消費税が非課税とされ、建物部分は課税になりやすい整理です。
土地と建物を一括譲渡する場合は、対価を合理的に区分して建物部分だけ課税する考え方が示されています。
区分方法は時価比や固定資産税評価額等に基づく按分などが例示されています。
| 対象 | 消費税の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 土地・借地権 | 非課税 | 国税庁 No.6931 |
| 建物 | 課税になりやすい | 国税庁 No.6931 |
| 一括譲渡の区分 | 合理的に按分が必要 | 国税庁 No.6301 |
課税事業者かどうかで総額が変わる
売却する法人が課税事業者かどうかで、建物部分の消費税の扱いが変わります。
免税事業者の判定や簡易課税の適用など、売却年に向けて選択の余地が出る場合があります。
売却が決まってから制度適用を変えられない場面もあるため、早めの確認が重要です。
- 基準期間の課税売上高の確認
- 特定期間の判定要件の確認
- 簡易課税の選択と届出期限
売買契約書の印紙税は契約金額で決まる
不動産の譲渡に関する契約書は印紙税の課税文書になり、契約金額に応じて税額が変わります。
印紙税額の一覧表は国税庁が公表しているため、まずは該当レンジを当てはめるのが確実です。
また不動産の譲渡に関する契約書については軽減措置に関する注記もあるため、作成年月日にも注意します。
- 課税文書の確認は国税庁の区分で行う
- 契約金額の記載がない場合も定額課税がある
- 軽減措置の適用期間に注意する
印紙税額の目安を表で素早く確認する
印紙税は契約書1通ごとに課税されるため、正本と副本の作り方でも実費が変わります。
契約金額帯が大きいと印紙税も上がるので、売却コストの見積りに必ず入れます。
税額レンジは国税庁の一覧表で確認できます。
| 契約金額 | 印紙税額の例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 国税庁 No.7140 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 国税庁 No.7140 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 国税庁 No.7140 |
法人ならではの会計処理と決算・申告の流れ

税率の前に、会計処理の形が整っていないと、売却益の算定も申告も崩れます。
固定資産売却の仕訳はパターンで押さえる
仕訳は会社ごとの勘定科目設計で違いが出ますが、骨格は共通です。
売却代金の入金、固定資産の除却、売却益や売却損の計上を、同じタイミングで整合させます。
消費税の処理は税込経理か税抜経理かでも形が変わるため、社内ルールを先に固定します。
| 論点 | 例 |
|---|---|
| 売却代金 | 未収入金または現預金で計上 |
| 固定資産の除却 | 取得原価と減価償却累計額を振替 |
| 損益 | 固定資産売却益または固定資産売却損 |
| 消費税 | 税抜処理か税込処理かで勘定が変動 |
売却直前に減価償却の最終調整をする
売却月までの償却をどこまで計上するかで、帳簿価額が変わります。
帳簿価額が変わると売却益が変わり、結果として法人税等の見積りも変わります。
固定資産台帳と総勘定元帳の突合をしてから売却益を確定させるのが安全です。
- 売却日までの償却費の計上範囲
- 耐用年数や償却方法の設定ミスの有無
- 資本的支出と修繕費の判定の整合
申告では別表調整が必要になる場面がある
会計上の損益と税務上の損益は、同じにならないことがあります。
交際費や寄附金、役員給与などの一般論に加え、不動産売却では関連費用の区分で差が出やすいです。
申告書では別表で加算減算を行い、課税所得を確定させます。
| 調整の起点 | よくある例 |
|---|---|
| 損金不算入 | 要件を満たさない費用計上 |
| 損金算入時期 | 計上時期のズレによる調整 |
| 消費税処理 | 税込経理と税抜経理の差異 |
| 棚卸資産との切り分け | 販売用不動産の扱いの差 |
税理士に依頼する場合でも社内で準備すべき資料
税理士に任せても、資料が揃っていないと判断が遅れて税額がブレます。
特に土地建物の内訳や按分根拠、譲渡費用の根拠資料は、早めに集めたほうが後工程が軽くなります。
売却後に慌てないために、契約前からチェックリスト化しておくのが効果的です。
- 売買契約書と重要事項説明書
- 固定資産台帳と減価償却明細
- 譲渡費用の請求書と領収書
- 土地建物の按分根拠資料
税負担を最適化する実務の選択肢

法人の不動産売却は「税率を下げる」よりも「課税所得のブレを減らす」ことが実務では効果的です。
売却タイミングと利益の平準化を考える
同じ売却益でも、他の事業利益が大きい年に重なると税負担が重く感じやすいです。
決算期の変更や売却時期の調整が可能なら、利益の山を平準化できることがあります。
ただし形式だけで動かすと否認リスクが出るため、経営上の合理性とセットで設計します。
- 当期の見込み利益と売却益の重なりを確認
- 資金需要と納税時期のズレを見積もる
- 金融機関提出資料の利益計画と整合させる
繰越欠損金やグループ内の損益と相殺できるか
欠損金があれば、売却益を欠損金で相殺して課税所得を圧縮できる可能性があります。
ただし欠損金の控除には制度上の上限や期間の論点があるため、事前に適用可否を確認します。
グループ内取引では時価や合理性の説明が必要になりやすいので、価格根拠の資料化が重要です。
| 論点 | 確認ポイント |
|---|---|
| 欠損金 | 残高、控除上限、期限の確認 |
| グループ内売買 | 時価根拠、契約条件の合理性 |
| 役員等への譲渡 | 利益供与とみられない設計 |
| 証憑 | 査定書、見積書、議事録の整備 |
土地建物の対価按分は消費税と法人税の両方に効く
土地は非課税で建物は課税になりやすいため、按分の仕方で消費税の額が変わります。
同時に、土地と建物で帳簿価額が異なるため、按分は売却益の配分にも影響します。
按分方法は合理性が求められ、国税庁の考え方として時価比や評価額比などが例示されています。
- 時価比による按分
- 相続税評価額や固定資産税評価額による按分
- 税務上の取扱いに沿った区分
- 根拠資料の保存
売却前に確認したい実務チェックリスト
最終的な税額は「売却益の精度」と「周辺税目の抜け漏れ」で決まります。
売却が決まってからだと修正が効かない論点もあるため、契約前の段階で網羅的に潰すのが理想です。
下記を埋めるだけでも見積りの再現性が上がります。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 固定資産の区分 | 土地と建物、付属設備の切り分け |
| 帳簿価額 | 台帳残高と償却の最終調整 |
| 消費税 | 課税事業者判定と建物課税の有無 |
| 印紙税 | 契約金額レンジと軽減措置の確認 |
| 譲渡費用 | 仲介、測量、解体、立退等の証憑整理 |
税率の目安を前提に手取りまで逆算しよう

法人の不動産売却では、税率は実効30%前後を起点にしつつ、会社の条件で上下する前提で見積もるのが現実的です。
次に、売却益の式を固定し、帳簿価額と譲渡費用の範囲を固めると、税額のブレが急に小さくなります。
さらに土地建物の按分、消費税の課税関係、印紙税などの周辺コストを足し上げると、手取りの精度が上がります。
最後に、納税時期と資金繰りまで落とし込み、売却後の投資や返済計画と一体で判断すると失敗が減ります。
不動産の金額が大きいほど、早い段階で税務と会計の前提を固めることが最大の節約になります。