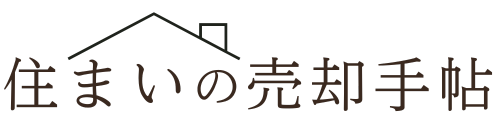生前贈与で不動産を受け取ったあとに売却すると、税金は「贈与の時」と「売却の時」で論点が分かれます。
よくある勘違いは、贈与税を払ったら売却時の税金が軽くなると考えてしまうことです。
本記事では、国税庁の一次情報をもとに、計算の流れと落とし穴、ケース別の選び方を整理します。
生前贈与で受け取った不動産を売却すると税金はどうなる?

結論として、税金は「贈与税」と「譲渡所得(所得税・住民税)」の二段構えで考えます。
売却時の判定では、取得費や保有期間を贈与者から引き継ぐ点が重要です。
税金は贈与の時と売却の時で別物になる
生前贈与で不動産を受け取った時点では、原則として受贈者に贈与税が関係します。
その後に不動産を売却すると、売却益に対して譲渡所得として課税されます。
同じ不動産でも、課税の入口が違うため「二重課税」とは扱いが異なります。
まずは論点を分けて、申告漏れを防ぐのが最優先です。
- 贈与の時:贈与税(暦年課税または相続時精算課税)
- 売却の時:譲渡所得(分離課税)
- 追加で起こりやすい負担:登記費用や地方税
売却時の保有期間は贈与者の取得時期を引き継ぐ
譲渡所得が「短期」か「長期」かで税率が大きく変わります。
相続や贈与で取得した土地建物の取得時期は、原則として贈与者の取得時期を引き継ぎます。
つまり、受贈者が持っていた期間が短くても、贈与者が長く保有していれば長期判定になることがあります。
判断の根拠は国税庁の「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」です。
| 確認する日付 | 贈与日ではなく贈与者の取得日が基本 |
|---|---|
| 参照 | 国税庁 No.3270 |
| 実務のコツ | 売買契約書・登記簿・購入時の領収書を先に集める |
取得費も原則として贈与者の取得費を引き継ぐ
売却益の計算は、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いて行います。
贈与で取得した不動産の取得費は、原則として贈与者が購入した代金などを基に計算します。
受贈者が負担した登記費用や不動産取得税などを取得費に含められる場面もあります。
取得費の考え方は国税庁の「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費」に整理されています。
- 基本:贈与者の購入代金・購入手数料など
- 追加:受贈者が支払った登記費用など(条件あり)
- 注意:建物は減価償却相当額を控除して計算
短期と長期の税率はここで差が出る
短期譲渡所得は、課税譲渡所得に対して所得税30%・住民税9%が基本です。
長期譲渡所得は、課税譲渡所得に対して所得税15%・住民税5%が基本です。
いずれも復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が上乗せされる扱いがあります。
税率の根拠は国税庁の譲渡所得の解説と、短期譲渡所得の税額計算のページで確認できます。
| 区分 | 税率の目安 |
|---|---|
| 短期 | 所得税30%+住民税9%(別途復興特別所得税) |
| 長期 | 所得税15%+住民税5%(別途復興特別所得税) |
| 参照 | 国税庁 No.1440/国税庁 No.3211 |
取得費が分からないときは概算取得費5%が使える
古い不動産だと、購入時の契約書や領収書が見つからず取得費が不明になりがちです。
取得費が分からない場合などには、売却額の5%相当額を取得費とする方法が示されています。
ただし概算取得費を使うと、実際より取得費が小さくなり税金が増えることがあります。
使う前に、贈与者側の資料や金融機関の履歴を一度洗い出すのが安全です。
- 探す資料:売買契約書、重要事項説明書、仲介手数料の領収書
- 見落としやすい費用:購入時の手数料、測量費、造成費
- 根拠ページ:国税庁 No.3202/国税庁 No.3258
贈与税を払っても譲渡所得が自動で減るわけではない
贈与税は、贈与という無償移転に対して課される税金です。
一方で譲渡所得は、売却による所得に対する税金で、計算の出発点が別です。
贈与税を払ったからといって、売却時の取得費がリセットされるわけではありません。
この前提を知らないと、想定外の譲渡所得税が発生して資金繰りが崩れます。
| 誤解 | 贈与税を払った分だけ売却時の税金が減る |
|---|---|
| 実務 | 取得費は原則として贈与者の取得費を引き継ぐ |
| 確認先 | 国税庁 No.3270 |
負担付贈与は贈与者側に譲渡所得が出ることがある
住宅ローンなどの債務を受贈者が引き受ける形の贈与は、負担付贈与として扱われます。
負担付贈与では、贈与者は負担額で譲渡したものとして譲渡所得の対象になり得ます。
受贈者側の贈与税だけでなく、贈与者側の所得税も論点になりやすい点が落とし穴です。
贈与契約を作る前に、ローン残高や担保関係を含めて必ず確認します。
- 典型例:ローン付き自宅を子へ名義変更
- 起こり得る課税:贈与者の譲渡所得、受贈者の贈与税
- 根拠ページ:国税庁 No.4426
まず押さえる生前贈与の税金と手続き

生前贈与の課税方式は大きく暦年課税と相続時精算課税に分かれます。
不動産では税金だけでなく登記や地方税も絡むため、順番を誤ると手間と費用が増えます。
暦年課税は基礎控除110万円を超えると申告が視野に入る
暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日)の贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて計算します。
基礎控除は贈与者ごとではなく受贈者ごとに年110万円という点が重要です。
不動産は評価額が大きくなりやすく、現金贈与よりも早い段階で申告が必要になりがちです。
税率は累進で、速算表を前提に試算して資金準備の目安を作ります。
- 基礎控除の考え方:国税庁 No.4410
- 税率と速算表:国税庁 No.4408
- 不動産は評価の前提が重要:路線価地域か倍率地域かを確認
相続時精算課税は年間110万円の基礎控除がある
相続時精算課税を選ぶと、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除がある取扱いが示されています。
基礎控除を超える部分は、原則として一律20%で贈与税を計算し、将来の相続時に相続財産へ加算します。
暦年課税へ戻れないなどの制約があるため、単に税率だけで決めるのは危険です。
制度の要点は国税庁の相続時精算課税のページと、改正のあらましで確認できます。
| ポイント | 特定贈与者ごとの枠で考える |
|---|---|
| 基礎控除 | 年間110万円(条件や時期の注記あり) |
| 参照 | 国税庁 No.4103/国税庁 税制改正のあらまし(PDF) |
夫婦間の居住用不動産の贈与は配偶者控除が論点になる
婚姻期間が20年以上などの要件を満たすと、居住用不動産の贈与で最高2,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は基礎控除110万円と別枠で使える取扱いが示されています。
ただし適用には贈与税の申告が前提となり、申告しないと控除を受けられません。
自宅の生前贈与を考える場合は、売却予定の有無も含めて同時に設計します。
- 特例の概要:国税庁 No.4452
- 店舗兼住宅などは居住部分のみ対象になることがある
- 申告で添付する書類はチェックシートでも確認できる:国税庁(PDF)
不動産の生前贈与は登記と地方税のコストも見落とせない
不動産は名義変更が必要で、登記をしないと売却手続きに進めません。
登記では登録免許税や司法書士報酬が発生し、資金が必要になります。
さらに不動産取得税など地方税が課税される場合があり、想定より現金が減りやすいです。
税金の試算は、贈与税だけでなく周辺コストも含めて行うのが安全です。
| 代表的な費用 | 登録免許税、司法書士報酬、必要書類取得費 |
|---|---|
| 地方税 | 不動産取得税(課税される場合がある) |
| 実務の順番 | 贈与契約→評価・試算→登記→申告の準備 |
売却時にかかる譲渡所得税の計算手順

売却時の税金は、譲渡所得の計算を正しく行うことが入口です。
生前贈与が絡むと取得費と保有期間の確認が難しくなるため、式を固定して資料を当てはめます。
譲渡所得は「売却額−取得費−譲渡費用」で考える
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
この計算は給与所得などと分けて課税される分離課税が基本です。
まずはこの式に沿って、入れる数字を資料から確定させます。
計算の考え方は国税庁の譲渡所得の計算ページで整理できます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 収入金額 | 売買契約書の売却代金など |
| 取得費 | 購入代金、購入手数料、改良費など(建物は減価償却控除) |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、測量費、建物解体費など(要件で判断) |
| 参照 | 国税庁 No.3202 |
取得費は贈与者の購入時資料を最優先で探す
生前贈与の売却で最も差が出るのは、取得費が証明できるかどうかです。
取得費は贈与者の購入代金などを基にするため、贈与者側の書類が強い証拠になります。
見つからない場合でも、固定資産税の明細だけで諦めず、金融機関や仲介会社の控えを探します。
取得費が不明なときの扱いは国税庁でも別ページで整理されています。
- 探す順番:売買契約書→領収書→重要事項説明書→金融機関の振込記録
- 建物は減価償却を控除するため、購入時の建物価額も重要
- 根拠ページ:国税庁 No.3258
譲渡費用は「売るために直接かかった費用」を中心に整理する
譲渡費用は、売却のために直接要した費用が中心になります。
引越費用や家具購入のような間接費は混ざりやすく、区分を誤ると否認リスクが上がります。
売却関連の領収書は用途をメモして保管すると、申告時に迷いません。
迷う費用がある場合は、税理士や税務署の相談窓口で確認してから計上します。
- 代表例:仲介手数料、測量費、境界確定費用
- 状況次第:解体費、立退料、違約金
- 注意:ローン完済手数料などは扱いが分かれやすい
税率判定は「譲渡した年の1月1日」で線を引く
短期か長期かは、所有期間が5年を超えるかどうかで判定します。
判定は譲渡した年の1月1日時点での所有期間を用いる説明が示されています。
生前贈与では贈与者の取得時期を引き継ぐため、ここでも引継ぎが効いてきます。
売却時期を年またぎで調整するだけで税率区分が変わる場合があるため、契約時期も含めて確認します。
| 判定の軸 | 5年超かどうか |
|---|---|
| 参照 | 国税庁 暮らしの税情報(土地や建物を売ったとき) |
| 実務の注意 | 売買契約日と引渡日で年が変わるケースを確認 |
生前贈与からの売却で損しやすい落とし穴

税金の制度を知らないまま進めると、贈与と売却の両方で損をすることがあります。
ここでは、実務で頻出の落とし穴を先回りして潰します。
名義変更が未了だと売却が止まる
不動産売却は登記名義人が売主として契約するのが基本です。
贈与のつもりで話を進めても、名義が変わっていないと売却の手続きが止まります。
急いで売りたい局面ほど、登記や必要書類で時間がかかりやすいです。
贈与の実行と売却活動の開始は、順番を明確にして並走させます。
- 先にやること:贈与契約書の作成と登記の段取り
- 売却側で必要:本人確認書類、権利証、固定資産税納税通知書
- 注意:共有名義や抵当権があると手続きが増える
取得費不明で概算取得費5%を使うと税負担が膨らむことがある
概算取得費は便利ですが、実際の取得費が大きい不動産ほど不利になります。
特に長期保有で地価が上がっている土地は、売却額が大きくなりやすいです。
その結果、取得費を5%にすると譲渡所得が過大になり税金が増えます。
贈与者の古い契約書を探す価値が高いのはこのためです。
| ありがちな状況 | 購入が古く資料が散逸している |
|---|---|
| 起こり得る結果 | 取得費が小さくなり譲渡所得が増える |
| 根拠 | 国税庁 No.3202 |
居住用の特例が使えると思い込んでしまう
マイホームを売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし特例は「居住用財産」としての要件を満たす必要があり、別荘や賃貸中の物件は対象外になり得ます。
生前贈与で受け取った後にすぐ売る場合、居住実態の要件を満たせないケースもあります。
要件の確認は国税庁のマイホーム特例のページで行うのが確実です。
- 特例の概要:国税庁 No.3302
- 同じ相手への売却など、適用できないケースがある
- 住民票の移動だけで判断できないこともある
負担付贈与や低額譲渡で課税関係が複雑になる
ローン引受けがあると負担付贈与となり、贈与者に譲渡所得が生じる可能性があります。
また時価とかけ離れた低額での譲渡は、税務上の評価や別の論点を招きやすいです。
家族間取引は書類が簡素になりがちですが、税務上は形式より実質で見られます。
一度こじれると修正申告や延滞税が絡むため、最初から設計します。
| リスクが高い形 | ローン付きで名義だけ移す |
|---|---|
| 起こり得る課税 | 贈与者の譲渡所得、受贈者の贈与税 |
| 参照 | 国税庁 No.4426 |
節税につながる選択肢をケース別に比較

節税は「制度を使うこと」よりも「最適なルートを選ぶこと」で差が出ます。
生前贈与と売却はセットで考え、相続との比較も含めて判断します。
贈与して売るか相続して売るかで有利不利が変わる
生前贈与は、贈与税の負担が先に発生する点が特徴です。
相続の場合は相続税の論点になりますが、売却時に相続税額の取得費加算の特例が関係する場合があります。
どちらが得かは、相続税がかかるか、売却益がどれだけ出るかで結論が変わります。
相続税が課税される場合の取得費加算は、国税庁でも要件が整理されています。
| 比較軸 | 先に税が出るか、後で税が出るか |
|---|---|
| 生前贈与 | 贈与税が先に発生しやすい |
| 相続 | 相続税が課税されると取得費加算の特例が論点 |
| 参照 | 国税庁 No.3267 |
夫婦間の自宅なら配偶者控除の特例が選択肢になる
自宅の名義を配偶者に移す目的が老後設計や相続対策であれば、配偶者控除の特例が候補になります。
最高2,000万円まで控除できる特例はインパクトが大きく、現金を残したまま名義を移せる可能性があります。
ただし売却予定が近いなら、贈与と売却の順番が逆効果になることもあります。
適用要件と申告の必要性を一次情報で確認してから進めます。
- 特例の根拠:国税庁 No.4452
- 申告が前提で、申告しないと控除できない
- 居住用でない部分が混在する場合は対象範囲を分けて考える
相続時精算課税は「将来の相続」とセットで設計する
相続時精算課税は、贈与時に一定の控除や税率がある一方で、相続時に加算される制度です。
将来の相続財産の規模や相続人の構成が変わると、想定より税負担が増えることがあります。
また一度選択すると暦年課税に戻れない制約があるため、柔軟性は下がります。
制度の要点は国税庁のページで、注記も含めて確認します。
| 向いている場面 | 将来の相続まで見通しが立つ |
|---|---|
| 注意点 | 選択後は暦年課税へ戻れない |
| 参照 | 国税庁 No.4103 |
売却前にやるべきチェックでミスと無駄を減らす
節税の前に、ミスをなくすだけで手取りが増えるケースは多いです。
特に生前贈与が絡むと、取得費資料と名義、負担付贈与の有無で論点が増えます。
売却活動を始める前に、チェック項目を短く固定して抜け漏れを防ぎます。
不明点は早めに専門家に投げるほど、修正コストが下がります。
- 取得費資料:贈与者の購入資料が残っているか
- 保有期間:贈与者の取得日が確認できるか
- 権利関係:共有・抵当権・ローン残高の有無
- 特例:居住用3,000万円控除の要件に当てはまるか
税金の全体像を押さえて最適な進め方を選ぼう

生前贈与の不動産売却は、贈与税と譲渡所得の両方を別々に整理するのが出発点です。
取得費と保有期間を贈与者から引き継ぐため、資料集めがそのまま節税につながります。
自宅の特例や配偶者控除、相続時精算課税などは強力ですが、要件と順番を間違えると逆効果になります。
売却時期が近いほど、名義変更や負担付贈与の論点で詰まりやすいので早めに設計します。
一次情報で根拠を確認しつつ、迷う点は税理士などの専門家に相談して手取り最大化を狙いましょう。